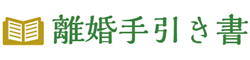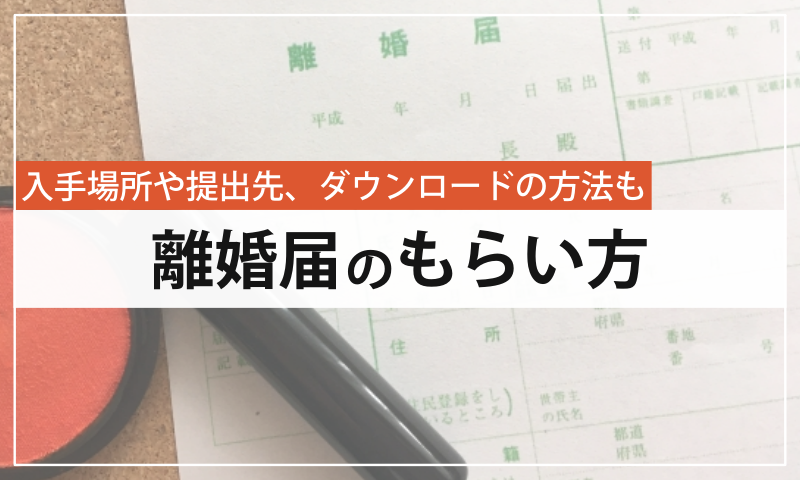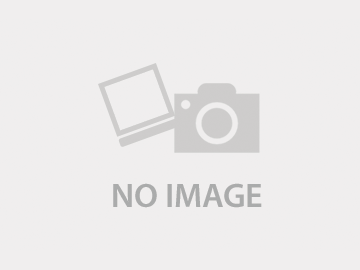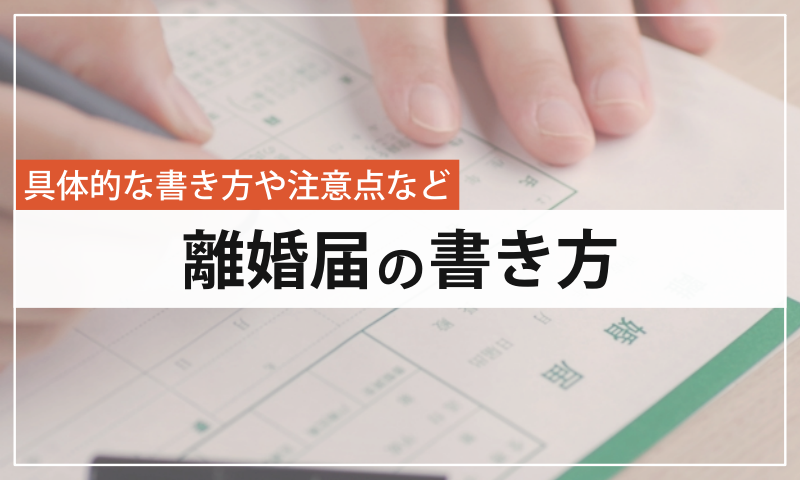
ここでは離婚届の書き方を分かりやすく丁寧に解説します。項目ごとの具体的な書き方や注意点などをピックアップしていますので、ぜひご参考ください。
インターネット上では全国共通となっている離婚届がPDF形式で無料ダウンロードできますので、事前に準備しておきましょう。
目次
離婚届にハンコ・印鑑は必要?

2021年9月の戸籍法改正により離婚届の押印が不要となりました。これにより協議離婚の場合、届出人および証人の署名のみで届出ができるようになっています。
ただ、法改正からかなりの期間が経過しているにも関わらず、ネット上ではまだ「押印が必須」と説明しているサイトが多いのも事実です。従来通り用紙に押印することは可能ですが、あくまで任意なので記載内容に不備が生じるということはありません。
印鑑は実印ではなく認印で問題ありませんが、シャチハタは使用できません。
書き方の見本サンプル
こちらは、法務省が記載例として公開している離婚届の見本です。例として、妻が元の名字に戻る場合のものですが、夫が名字を戻す際の記載例はこちらより確認できます。
離婚届の書き方をわかりやすく

離婚届の項目ごとの具体的な書き方を詳しく説明しています。上記の見本も参考にしていただくと、よりわかりやすく簡単に書けるのではないでしょうか。
氏名の書き方
氏名は、離婚後に名字が変わるとしても離婚前の名字で記入します。
また、生年月日は西暦でなく、和暦(昭和、平成など)から書きましょう。ただし、S、Hなどのアルファベット表記で記載してはいけません。
住所の書き方
夫婦ともに住所欄には住民票に登録されている住所と、世帯主の氏名を記入します。住所は省略せず、住民票と同じく都道府県名から正確に記入してください。
また、別居していても住民票を移していなければ、夫妻どちらの欄も書く内容は同じです。
本籍の書き方
夫婦の本籍地と筆頭者の氏名を記入します。本籍地は、戸籍謄本に登録されている本籍地を都道府県から正確に記入してください。
また、筆頭者の欄には戸籍謄本の1番はじめに記載されている方の名前を記入しましょう。
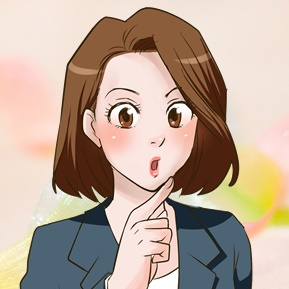
筆頭者は、婚姻届を提出した際にどちらの名字にしたかによって決まります。夫の名字を選んでいれば夫が筆頭者、妻の名字を選んでいれば妻が筆頭者ということになります。
父母及び養父母の氏名・続き柄の書き方
自身と相手の父親・母親の氏名をそれぞれ記入します。父親または母親が亡くなってしまっている場合でも書く必要があります。
また、続き柄は戸籍に記載されている通り(長男や二女など)に記載します。
離婚の種別の選択
話し合いによって決まった離婚は「協議離婚」を選択しましょう。裁判での離婚は当てはまるものを選んでください。
婚姻前の氏にもどる者の本籍の書き方
離婚届によって戸籍が異動するのは、筆頭者でない方だけです。通常は、両親の戸籍に戻るのが一般的です。
しかし両親とも他界するなどして除籍となり、もどる戸籍がない場合は「新しい戸籍をつくる」の項目にチェックを入れます。また、お子さんがおられる場合で、お子さんを自分の戸籍に入れたい場合も新しい戸籍をつくるを選択しましょう。
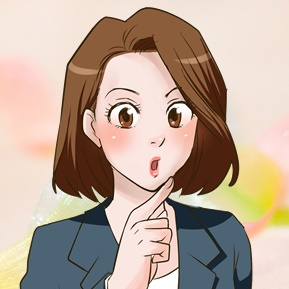
新しい戸籍をつくるを選択したときの本籍地は、地番(土地を特定する番号)があるところなら日本全国どこに置いても良いとされています。もちろん、離婚前に置いていた本籍地と同じでも問題ありません。
未成年の子の氏名の書き方
未成年のお子さんがいる場合にのみ記入します。親権者になる方にお子さんの名前を書きましょう。
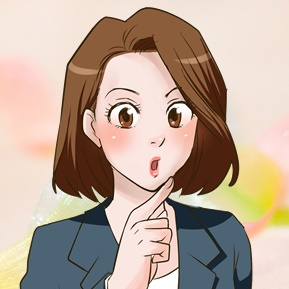
親権が決まっていないと離婚届を受理してもらうことができないので、離婚届を出すまでにはしっかり決めておかなければいけません。
同居の期間の書き方
結婚前から同じ家に住んでいたならその時期を記入します。同居することなく結婚した、もしくは一緒に住み始めた日がわからないというときは、結婚式を挙げた日を書きましょう。結婚式の日も曖昧だという場合は、だいたいの日付でかまいません。
また、「別居したとき」の部分は離婚届提出までに別居をしていないなら空欄にしておきましょう。
別居する前の住所の書き方
2人が離婚前に住んでいた自宅の住所を記入します。別居をしていないなら空欄でかまいません。
別居をする前の世帯と主な仕事と夫妻の職業の書き方
夫・妻どちらか収入の多い方の仕事内容で、当てはまるものをチェックすれば良いです。選択が難しい場合はだいたいの感覚で問題ありません。
職業記入の欄は、国税調査がされる年の4月から翌年3月までの間に離婚届を提出するときのみ記入します。普段は書く必要がありませんので空欄で大丈夫です。
届出人署名の書き方
夫・妻それぞれの氏名を記入します。必ず本人が署名しなければいけません。提出のときに1人であったとしてもどちらの署名も必要ですので、忘れないよう注意しましょう。
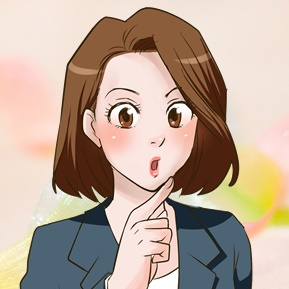
冒頭で説明のとおり、印鑑を押す必要はありません。
証人の書き方
書き方はご自身が書いたものと同じです。
生年月日は西暦でなく、和暦(昭和、平成など)から書きましょう。住所・本籍は省略せず、都道府県名から正確に記入してもらってください。本籍がわからない場合は住民票を取り寄せてもらうなどして書いてもらいましょう。
証人の欄は裁判での離婚でない限り必須です。書かないと受理してもらえません。
18歳以上であれば自身のお子さんでも、友人・知人などどなたでもかまいませんので、必ず2名分の署名を用意しましょう。
証人になったからといって、法的な責任を問われるなどは決してありません。
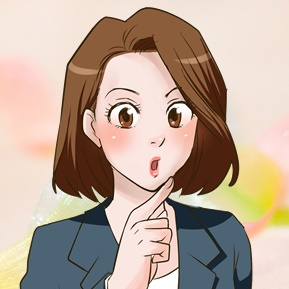
離婚する本人同士が虚偽の署名をしてしまうと「文書偽造」などの罪を犯すことになります。どうしても頼める人がいない場合は、行政書士や弁護士、代行サービスなどをうまく活用しましょう。