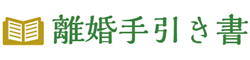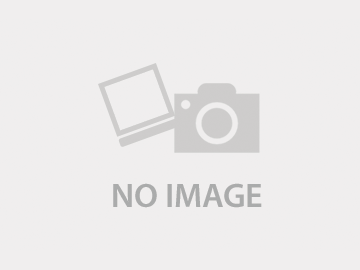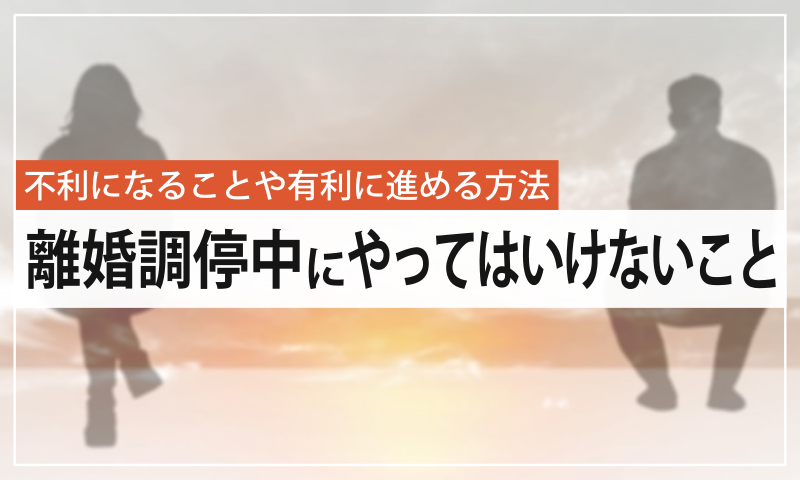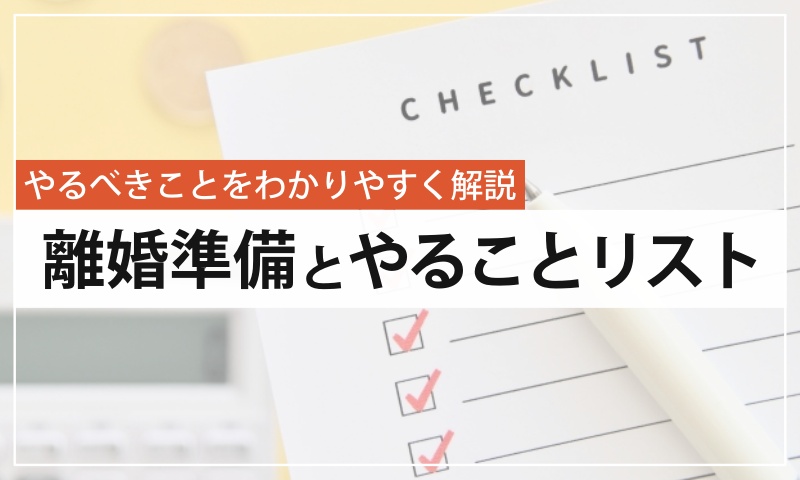目次
離婚するときに年金って分割手続きできるの?
可能です。
年金とは何?簡単に解説
年金は大きく分けて国民年金と厚生年金の2つに分かれます。
国民年金とは20歳以上60歳未満の国民全員に納付義務がある年金で、受給金額は年金を納付した期間に基づいて支払われます。
それに加えて公務員や企業に勤めている人、細かく言うと法人と常時5人以上の従業員がいる個人事業者が加入しなければならない仕組みになっているのが厚生年金です。これは給与に基づいて納付することになっていて、人によって金額が変わるのが国民年金との違いです。
つまり年金というものは、厳密に言えば老後に何もしなくてもお金がもらえるというものではなく、今現在から老後に向けて貯蓄していくものとイメージしておくと良いでしょう。
離婚時の年金分割とは?
年金分割とは、婚姻期間中に納めた厚生年金の納付実績を夫婦で分け合う制度です。専業主婦の方も共働きの方も受け取ることができ、多い方から少ない方へと分けられます。
年金分割が必要な理由
厚生年金は給与額に応じて支払うことになっています。つまり給与のない専業主婦の妻は給与のある会社員の夫に比べて将来、受給できる年金の金額に差が生じてしまうのです。そこで夫婦間の差を埋めるために夫が妻の厚生年金を扶助すことが出来るようになっています。そうすれば将来の年金受給額の差が少なくなり、老後の生活において同じような生活水準を保つことができるのです。ですが年金を受給する前に離婚したとなると結局妻の年金受給額が少なくなってしまいます。その差を補うためにある制度が年金分割です。年金分割は共働きの夫婦でも行うことができ、給与の多い方から少ない方へ分割される仕組みになっています。年金分割の対象になる期間は婚姻期間中に相手が納付していた期間です。その納付した金額が当事者の納付実績となります。
専業主婦と共働きでは分割方法が異なる
夫に厚生年金を扶養してもらっていた専業主婦で、20歳以上60歳未満の人を3号被保険者といい、対して扶養していた側のことを2号被保険者といいます。
3号被保険者が2号被保険者に年金分割を請求する場合、双方の合意や裁判をすることなく分割してもらえます。これが3号分割制度です。分割割合は一律2分の1とされています。注意点として平成20年4月1日に始まった制度であるため、それ以前に離婚している場合は3号分割制度を利用できません。
共働きの方は当事者間での話し合いによる合意分割により年金を分割します。場合によっては合意分割と3号分割の両方で分割する場合もあります。会社勤務していた時期と専業主婦の時期がある場合はそれぞれの年数分、分割することになっています。
専業主婦でも年金はもらえる?
専業主婦でも年金は問題なくもらえます。
ですが、専業主婦と共働きの人とで受給できる年金の金額にかなりの差があります。その理由をお話します。
もらえる金額の差は厚生年金を納付しているかどうか
老後、受給できる金額に大きな差が出るポイントとなるのは厚生年金を納付したかどうかです。
国民年金では所得関係なく一定の金額を納付するため、受給出来る金額に差が出ません。ですが厚生年金は個人によって納付した金額に差が出るので、その影響を受けて年金の総受給額に差が出るのです。
2022年4月の時点での国民年金の受給平均額は、月額5.6万円となっています。20歳から60歳の40年間一度も忘れることなくきっちり収めた場合、約6.5万円を受け取ることが出来ます。
これよりも勤務年数および納付年数が短い場合は、夫婦共働きであった方よりも受給できる金額が少ないということを理解しておいたほうが良いでしょう。
生命保険文化センターからのデータによれば、老後の平均的な生活費は月に約29万円であるのに対し、平均的な後の生活を送る上で必要とされる生活費は最低でも月額22.1万円となっています。さらに、ゆとりある生活を送るにはこれに月額14.0万円を上乗せした月額36.1万円が必要とされています。
つまり、専業主婦としてもらえる年金の最大額を受け取ったとしても、
- 夫婦2人が老後を過ごすのに最低限必要な生活費22.1万円/月に対し、約16.6万円不足する
- 夫婦2人がゆとりある老後を過ごすのに必要な生活費36.1万円/月に対し、約30.6万円不足する
となってしまうのです。